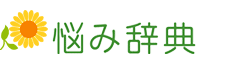1-20 卒業
- 2011年4月 2日(土) 20:15 JST
-
- 投稿者:
- 尾崎 宗一郎
-
- 閲覧数
- 3,123
{ 好き }という言葉。
いつも心の中で唱え、迷いの中にいた杉浦。
しかしその躊躇がいつしか機会をなくしていた、、、そのことにある日、気づいた。
いつしか優子たちは姿を現さなくなっていたのである。うっかりしていた。
優子たちが大学の卒業時期だったことにまったく気づいていなかったのである。
いつまでも在学しているという錯覚。その思い込みに自分を責めたてた。
大学の事務所に尋ねてみて「個人情報ですから」という一言で一蹴されたのはあたりまえのことだった。
その後の杉浦は身のおきどころがなく、店に勤務しても遠くを見つめるもののよにして、優子たちがウファに
訪れるのを待ち続けていたのだった。ほかにいくつか方法はあったのだろうが、この店で待ち続ければ、
優子や優子と一緒に訪れていた人たちの誰かが訪れてくれるものだろうと思った。
しかし現実はそれほど甘くはない。待ち続けているうちに自分自身の馬鹿さかげんに気づくことになる。
しかし杉浦にしてみれば、ほかに方法を思い浮かばず、ひたすら待ち続けていたのである。
いつか来てくれる。優子の友達でもいい。あの仲間の人たちの一人でも来てくれさえすればと。
その想い、毎日の切ない焦燥感がうねりをあげて身を焦がしていく。
誰かが入店するとすぐに顔を向いてしまい、つい出入り口が気になってしまう。夜になるとその哀しさは
より増し布団の中で泣いた。
だが、その苦しみを癒してくれたものがあった、、、。