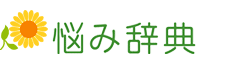1-22 久我さん
- 2011年4月21日(木) 20:44 JST
-
- 投稿者:
- 尾崎 宗一郎
-
- 閲覧数
- 3,438
杉浦は二人のすぐそばまできた。
「あの、、、たしか久我さんでしたよね」と絞り出すような声をだした。が、声が細い。
「あら、なんで私の名を」と優子はキョトンとして杉浦の顔をまじまじと見上げたのだった。
その愛らしい眼差しに「いえあの、、、あの、、、」と答えにならない返事をし「いえ、以前、学生でいらしたころ、久我さんたちがいらっしゃっていたときのことを思い出したので、声をかけてみようと思ったのです。あのころ、ちょくちょくご利用いただいてましたから、、懐かしくなってしまって」
「まあ、、、ありがとうございます。そうですよね。 もうあれから、ずいぶんになりますものね。その節はいろいろとお世話になりました」と優子は軽く、お辞儀をした。向かいに座っている早苗も軽く頭を下げ杉浦を見つめている。
杉浦は優子のそのなつかしい声を聞いて本当にめまいをしそうになった。優子の向かいに座っている早苗のことは目に入らない。そんな様子に早苗がクスクスと笑い出し、「そういえば、あのころ、背の高い感じのいい人だなと思っていたんですよ」と早苗は優子と顔を見合わせながら言った。
「あのころはあまり、お話する機会がなかったですね。こちらのほうには、よくいらっしゃるのですか?」と思い切って聞いてみたのである。
「そうですね。あれからあまり機会がなかったのですけれど、今日はこちらのほうに用事がありまして、それにここが懐かしくなって、、」
「ありがとうございます。またこちらにいらっしゃるご予定はあるのですか?」ともう切り出してしまったのである。
「えぇ、そうですね。また近々、予定がありますので、伺うと思います」
「本当ですか?」大きな声を出し、まるで子供のような杉浦の返答だった。あまりの単刀直入さについ優子も微笑みながら答えた。「ここはいつも感じのいいお店ですよね」その返事にどう応えていいかわからず杉浦は照れに照れてその場を去ってしまった。